

秋吉名誉理事長が英国赤十字社からセラピューティック・ケアの日本での普及を託されてから、約25年が経ちました。
セラピューティック・ケアは、相手の方の心にそっと寄り添い、手のぬくもりを通して、千の言葉よりも豊かな慰めと共感を届けます。そして何より、私たちも同様に癒されていることを実感できます。なんと温かい、優しい気持ちになれるのだろうと。
現在、仲間が全国に約900名おります。「すべての人々に尊厳と幸せを」という協会理念のもと、ミッションとビジョンを掲げて、デイサービス・有料老人ホーム等の高齢者施設へ、産後ママへのケア、ワークショップを通しての子育て支援、子ども食堂やコミュニティカフェで地域の方へと、手のぬくもりをお届けしています。
いつでも、どこでも、どなたにでも、ぬくもりを提供する事ができるケアを、ぜひ体験してみてください。必要とされる全ての方々に、幸せをお届けできますように。
プロフィール
北海道小樽出身、札幌在住。
講師、Complementary Therapist( CT) 、インファントセラピスト指導講師、さっぽろ支部長
結婚後45歳で専業主婦から介護職員として社会復帰し、介護福祉士・介護支援専門員・認知症ケア専門士の資格を取得。
2011年通信講座(第1期)でセラピューティック・ケアに出会い、ボランティア活動を始める。
2014年北海道支部を設立し、2019年からさっぽろ支部ととまこまい支部となる。
好きなことは、知らない土地を旅すること、音楽を聴きながらボーっとすること、でも1番好きなのはやっぱり、ライフワークであるセラピューティック・ケアで笑顔に出会うこと。
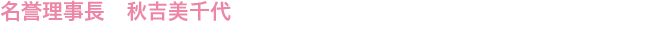

「ミセス秋吉、あなたにこのケアを託すわ」
それが、私が初めてセラピューティック・ケアに出逢った1999年9月、このケアの考案者のお一人であるサイアン・スコット女史から、テキスト一式と共にことづけられた言葉でした。
スコット女史からは、その前年に当時の美智子皇后が英国赤十字社を訪問された際にセラピューティック・ケアを学ばれたこと、「日本国民がこのケアを知ったらどんなに喜ぶ事でしょう」とおっしゃられたこと、それ以降で最初にレクチャーを受けた日本人が私だということもお聞きしました。そして、ぜひこのケアを日本でも広めてください、と。
それから25年。日本ではゼロからのスタートでしたが、これまでに北海道から沖縄まで、セラピューティック・ケアの講座や講習を通して50,000人以上の方々との出会いがあり、今では日本中に広がりました。生老病死すべての場面でケアが取り入れられ、喜んでいただいています。
新理事長の武藤と手を携え、笑顔に出会う喜びを心の糧として、協会のビジョンとミッションを遂行していきます。
プロフィール
1938年 佐賀県生まれ、佐賀県出身。
福祉コーディネーター(放送大学)、保育士資格保有。
セラピューティック・ケア協会の講師代表として各種講演・講習を行い、人材育成や普及啓発、小中学校の福祉体験授業支援に努めるほか、子育て支援にも力を注ぐ。
2020年11月 令和2年度 太宰府市市民活動賞受賞(社会福祉への尽力)
○福岡県レクリエーション協会理事
○太宰府市環境審議会委員
○日本ホスピス在宅ケア研究会会員
○日総研通信講座セミナー講師
個人Facebook
https://www.facebook.com/michiyo.akiyoshi.3
著書
○ 「ほほえみに出会いたくて ~ビューティーケア 輝きながら老いるために~」(新風舎/1999年)
○ 「~英国発セラピューティック・ケア~ 両手で伝えるやさしいコミュニケーション」(木星舎/2003年)
○ 「手のぬくもりは心のぬくもり セラピューティック・ケア 出会いのドラマ」(木星舎/2013年)




 秋吉名誉理事長が英国赤十字社からセラピューティック・ケアの日本での普及を託されてから、約25年が経ちました。
秋吉名誉理事長が英国赤十字社からセラピューティック・ケアの日本での普及を託されてから、約25年が経ちました。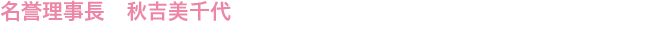
 「ミセス秋吉、あなたにこのケアを託すわ」
「ミセス秋吉、あなたにこのケアを託すわ」